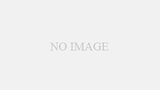私自身、やはりマネジメントの中で苦慮したのは、部下のモチベーション管理です。
私自身が基本的にモチベーションが高い、というか士気が高い、というか仕事に対しては成果=自分に利益になるという前提で動くので、ミッションは何が何でも達成させる気満々です。
ただマネジメントする以上は私自身だけでなく、部下やチーム・組織全体のモチベーションを適切に管理できる事が望ましいですし、それを常に意識していたものです。
ところで「士気」と「モチベーション」ってそれぞれどんな意味でしょう。
厳密には同じではなく、
□モチベーション
仕事や勉強などへのやる気
□士気
戦場(現在ならスポーツなども含め)での戦意や精神的な高揚
ほんのり違っているのですが、いずれにしても自分自身のコントロールならまだしも自分以外(主に部下とか)のコントロールは大変ですね。
ここで「士気」に着目してみましょう。
主に古代における戦場において、士気(=戦意)は重要でして、士気が高いと数倍の力を発揮し士気が低いと本来の力をまったく発揮できない。
そんな中で現代以上に大将の腕っぷしが兵士達の士気に大きく影響したようです。
要は大将がすんごい豪傑であれば兵士達は「こんな強え人がいるなら勝てるぞ!」と精神的に高揚(興奮)するので、おなじみ三国志で言えば「呂布」とか「関羽」とか「張飛」といった名だたる豪傑達が戦場に出ると味方の士気は上がる訳です。
一方で彼らと対する敵軍は逆に士気が下がるのです。
そのため、ゲーム風に定量的に表現すれば、基本が50だとして味方は彼らがいると士気+20で相手は士気が-20になり、味方と敵の士気の差は40に開く訳ですね。
また智将などの将軍も、開戦前に兵士達の前で演説し鼓舞する事で士気を高めます。
例えば君主達の演説例(と、言われている)を見てみると、
□曹操
『(官渡の戦いより。相手は曹操軍よりも強大な袁紹軍)我々は少数だが、敵は慢心している。我らが一致団結すれば、勝利は我々のものだ』
□劉備
『(益州攻略より。相手は同族の劉璋)民を苦しめる暴政を倒し、平和を取り戻す』
□孫権
『(赤壁の戦いより。相手は数倍の兵力を擁する曹操軍)曹操の大軍は恐るるに足らず。我らが水戦の利を活かせば必ず勝てる!』
上記を見ると曹操や孫権は劣勢に怯える家臣達に対し、自軍が少数でも有利な点があるぞ、と強くアピールしていますし、劉備は大義(最高の道義)は我らにあるぞ、これは侵略ではない、という自軍の正当性をアピールしています。
このように、古代の戦争は特に将軍の器量で兵士達の士気をコントロールしていたように見えます。
後がない事を表す「背水の陣」で有名な、前漢の功労者・韓信は、この背水の陣も正に兵士達に後が無い(背後が川なので足場が悪く動きにくい=逃げにくい)事を強調し、退くことができないと思わせる事で死に物狂いにさせ、結果奮起させ勝利に導いています。
このようにポジティブだけでなく、ある種ネガティブな方向でも、数万の兵士達のメンタルコントロールによって成し遂げる事は文献などにも多々残っています。
□今回のポイント
ポイント、と掲げていますが、決して私自身が必勝のモチベーションコントロールがあるぞ!という話は無くてですね・・・。
結局このモチベーション管理は難しいのです。
何せ人が相手ですから。
ただ、何かを成そうとする時、そこまで仰々しくせずとも目標を達成させるためにも、やはり前提としては「熱量」が無ければ無理だというのが私の持論です。
別に熱血教師の如く、とは言いません(昔のドラマみたいな熱血教師なんて現代じゃNGが多すぎる)。
それでも目標を達成させる事について、「上から言われた」とか「やらないと評価下がる」とか何というか他人事や兵士の心情みたいな事を部下に言っても響かないと思っています。
だからこそ『俺は目標を達成させたいんだ!それが俺だけでなく貴方を含めたチーム全体にメリットある唯一無二の事だからだ!』くらいには伝えます。
そこを変にかっこつけて冷めるのも結構ですけど、そんなところで冷めて何一つ良い事ないです。
経験上。
なので結論、必勝法は未だに模索中ですが、それでも常に熱量を意識している、というお話です。